こんにちは、うさぎ店長です🐇
今回は「店舗運営に活かせる行動経済学」をテーマに、私が現場で取り入れて効果を感じた5つの考え方を紹介します。
「行動経済学は最強の学問」というのをyoutubeでたまに見ます。
最初は心理学は難しそうだし営業に直結しないと考えていましたが、「影響力の武器」を読んで考え方が変わりました。
行動経済学とは、人が“合理的じゃない選択”をする理由や傾向を分析する学問。つまり、“お客様やスタッフがなぜそう動くのか?”の裏側を知ることで、売上・満足度・職場環境を改善できるんです。
難しい理論は一切ありません。行動経済学検定を合格したうさぎ店長が現場で「すぐ使える」視点だけをまとめました。
(でも合格したのは1級ではなく2級ですw)
1. デフォルト効果|“最初に提示された選択肢”が選ばれやすい
人は、最初に見た選択肢や設定を変えずにそのまま受け入れる傾向があります。
✅ 店舗での活用例
- ランチセットで「ドリンク付き」がデフォルトになっていると注文率UP
- アプリ登録画面で「メルマガ受け取り」が初期設定にあると登録率UP
- ポップで“おすすめ”として先に表示するメニューが選ばれやすい
最初に何を見せるか、何を標準にするかが、売上を左右します。
2. 選択肢のパラドックス|“選択肢が多すぎると”逆に選べなくなる
人は選択肢が多いと、迷って疲れてしまい、結局「何も選ばない」ことがあります。
✅ 店舗での活用例
- メニューをジャンル別に整理し、見せる数をしぼる
- 売り場のPOPに「迷ったらこれ!」とおすすめを明示
- オプション商品は“3つまで”に絞って提案
「選ばせすぎない」ことで、お客様は安心して選べるようになります。
3. アンカリング効果|“最初に見た価格や情報”に引っ張られる
人は最初に見た数字を基準に、その後の判断をしてしまいます。
✅ 店舗での活用例
- 高価格帯の商品を“先に”見せてから、お得な商品を案内(「安く感じる」)
- ポップで「通常価格:980円 → 特別価格:780円」のように比較を見せる
- セット販売で「単品価格」も記載し、割安感を演出
「比べる対象を用意する」ことで、価値を伝えやすくなります。
4. ハロー効果|“一つの印象”が全体の評価に影響する
人は、相手の一部の印象から“全体”を判断してしまいます。
✅ 店舗での活用例
- 店舗入り口をきれいに保つだけで「丁寧な店」と感じてもらえる
- スタッフの第一声の挨拶が良いと「対応も良い」と思われやすい
- 高級感のあるPOPやBGMで「品質が良さそう」に感じさせる
第一印象づくりが、お店全体の評価を左右するんです。
5. 損失回避バイアス|“得するより損したくない”という心理
人は「得られる喜び」より「失うことの痛み」を強く感じる傾向があります。
✅ 店舗での活用例
- 「今だけ」や「残り3名様」などの限定表現で即決を後押し* 「◯◯を買わないと損するかも」と伝える商品説明
- クーポンの有効期限を明記して“使い忘れ=損”と印象づける
損したくない心理を刺激することで、行動を後押しできます。
【まとめ】“選ばせ方”が、売上と満足度を変える
行動経済学は、「人がどんな時に“動くか・迷うか・満足するか”」を読み解くツール。
今回紹介した5つは、すべて店舗現場で簡単に使える考え方ですが、そのまま使えるものではありません。行動経済学のパターンを見ながら「あれ?これウチのお店のここで使えるかも!」と気づきを得るものだと考えています。
以下は簡単にそれぞれの効果を一言でまとめたものとなります。
- デフォルト効果 → 最初の選択がカギ
- 選択肢のパラドックス → 減らす勇気を
- アンカリング効果 → 比べさせる
- ハロー効果 → 第一印象で得する
- 損失回避バイアス → 「損したくない」を刺激
もし今、売上や満足度に伸び悩んでいたら、「人の選び方」にヒントがあるかもしれません。
行動経済学を是非みなさまの現場でも活かしてみてください。
— うさぎ店長 🐇
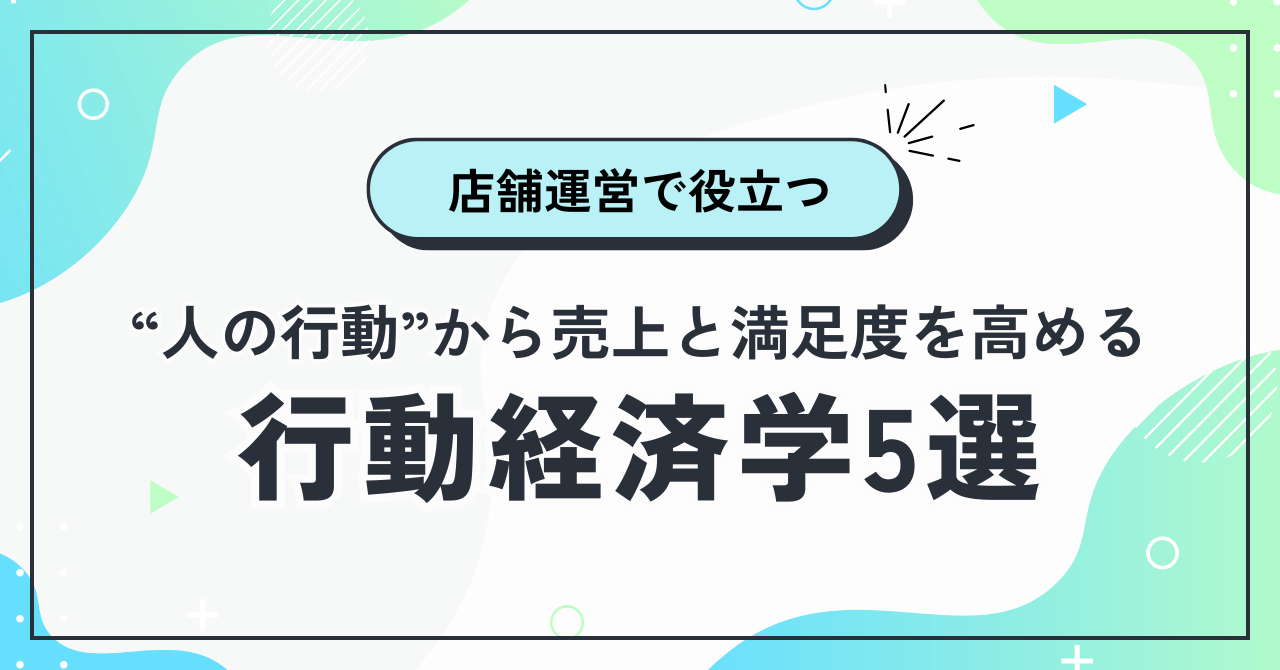

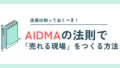
コメント