こんにちは、うさぎ店長です。
今回は「AIDMA(アイドマ)の法則」について、店長の視点から解説します。「名前は聞いたことあるけど、店舗運営でどう活かせばいいの?」と思っている方もいるのではないでしょうか。
「売れる店舗には仕組みがある」
AIDMAはまさに、その“売れる仕組み”を作るためのヒントが詰まっています。
この記事では、AIDMAの基本から、現場での応用方法、そして私自身の体験談まで交えながら、わかりやすく解説していきます。新任店長からベテランの方まで、きっと何か発見があるはずです。
1. そもそもAIDMAの法則って何?
AIDMAの法則とは、1920年代にアメリカのサミュエル・ローランド・ホールが提唱した「消費者が購入に至るまでの心理的なプロセス」のこと。
各段階の頭文字をとったもので、それぞれ以下の意味を持ちます。
【 A | Attention(注意) 】
商品やサービスに気づく。まずは「存在を知ってもらう」ことが重要。
【 I | Interest(関心) 】
気になった商品に興味を持つ。「もっと知りたい」と感じさせる段階。
【 D | Desire(欲求) 】
「欲しい!」「買いたい!」という感情が芽生える段階。
【 M | Memory(記憶) 】
購買の前段階で、記憶に残っている状態。タイミングが来たら買う可能性あり。
【 A | Action(行動) 】
実際に購入というアクションに至る。
2. 店舗現場ではどう活かす? 〜AIDMA分解のすすめ〜
現場では「どうすればもっと売れるのか?」「来店してもらうには?」という問いに対して、AIDMAの各フェーズに分けて考えると、具体的なアイデアが生まれやすくなります。
たとえば――
✅ Attention(注意):まず“気づいてもらう”こと
【現場実例】
- 看板をリニューアルし、通行人の足を止めるデザインに変更
- SNSでキャンペーン動画を配信して来店を誘導
- お客様の目線の高さにポップを設置し、新商品に目を向けてもらう
▶ ポイント:「存在を知られていない商品は、ないのと同じ」。まずは視覚的な工夫やSNSを活用して、“存在に気づかせる”ことが第一歩です。
✅ Interest(関心):気になってもらう工夫を
【現場実例】
- 商品のこだわりをPOPにして表示(原材料、製造地など)
- スタッフが「これ、実は私も買ったんですよ」と一言添える
- 商品サンプルを使って“試してもらう”
▶ ポイント:関心は“きっかけ”で高められます。売り場に説明がなければ、商品はただの物体。店長は「なぜこの商品を仕入れたのか」を伝える意識を持つと、お客様の興味を引きつけやすくなります。
✅ Desire(欲求):欲しい!と思わせる
【現場実例】
- お客様の「困りごと」に直結する訴求(例:足が疲れやすい方に→疲労軽減インソールPOP)
- 残り在庫わずかなどの“希少性”を訴求
- お客様の“理想の姿”を描く提案(例:快適に過ごしたい→汗をかいても快適なシャツ)
▶ ポイント:人は「自分に必要」と思えば買います。商品のスペックではなく「その人の未来が変わるかどうか」を伝えるのがコツです。
✅ Memory(記憶):思い出してもらう
【現場実例】
- LINEクーポン配信で「次回来店」の動機づけ
- レジで「次回は〇〇もご一緒にいかがですか?」と声がけ
- 商品に関連したミニ冊子・QRコードを渡して家で再確認できる導線
▶ ポイント:一度「いいな」と思った商品でも、記憶に残らなければ忘れられます。アフターフォローやSNSなど、接点を継続させる工夫をしましょう。
✅ Action(行動):最終的に買ってもらう
【現場実例】
- レジ横で“ついで買い”を誘う商品の配置
- 買い物カゴの中身を見て、「セットで使うと便利ですよ」と提案
- キャッシュレス対応でスムーズな決済環境
▶ ポイント:行動を後押しするには、“不安や面倒”を極力排除すること。「買いたい」気持ちが冷めないうちに、決済までスムーズに誘導できる仕組みを作りましょう。
3. 店長の仕事は「買いたい仕掛け」を用意すること
AIDMAを分解して見えてくるのは、購買は偶然ではなく「意図的に設計できる」ものだということです。
例えば、私はかつて新人スタッフにこう伝えました。
「売れないのは“商品”じゃなくて“売り方”だよ。AIDMAのどこが欠けてるか一緒に見直そう。」
この言葉をきっかけに、売場担当が自分から改善案を出すようになり、1ヶ月後には売上が前年比120%まで回復した事例もあります。
4. 店舗×AIDMA まとめ
✅フェーズ 店舗での意識ポイント例
Attention(注意) まず目立つか?通行人や来店者が気づいてるか?
Interest(関心) 商品の魅力が伝わっているか?触れるきっかけはあるか?
Desire(欲求) 買いたい気持ちを起こせているか?響く言葉や体験があるか?
Memory(記憶) 忘れられない仕掛けがあるか?また思い出せる導線は?
Action(行動) 実際に買うまでスムーズか?決済・声がけの工夫は?
■ 最後に:AIDMAを“仕組み化”しよう
もしあなたが「現場を改善したい」「スタッフにも売る力をつけさせたい」と思っているなら、AIDMAを“毎日のルーティン”に組み込むのが近道です。
朝礼でAIDMAに沿った売場改善案を共有する
POP作成の際に「今どのフェーズを狙うのか?」を確認する
こうした使い方を習慣化すると、店全体のレベルが確実に上がっていきます。
👣 まとめ
AIDMAは100年以上使われている“購買心理の公式”
店長の仕事は「売れる仕掛け」を整えること
どんな商品もAIDMAに当てはめて考えると改善案が見える
毎日の現場で、POPや接客の精度を上げるツールとして活用できる
AIDMAはマーケティング理論ですが、現場の第一線にいる店長こそ活かせる知恵です。
ぜひ、明日の売場から取り入れてみてください!
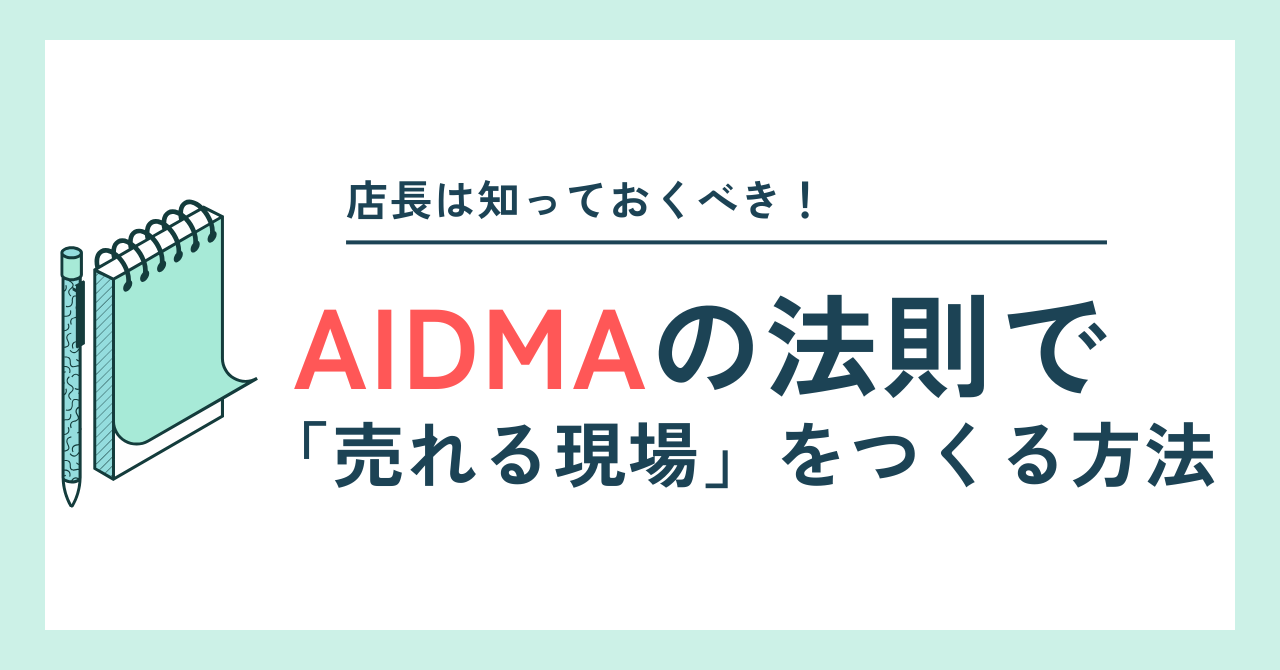
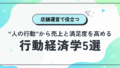
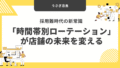
コメント