お店をもっと良くしたい!
でも何をしたらいいかわからない。。。もっと詳しく言えば「何から手をつければ良いかわからない」というのは私だけではないと思います。
そんな皆様のために「AIDMAの法則」をお伝え致します。
実はこの法則は100年前に提唱され今でも広告やマーケティングの世界で活用されている必ず覚えておかなければいけない概念となります。
AIDMAの法則とは
それでは早速、「AIDMAの法則」について説明します。
AIDMAは以下の5つの段階の頭文字をつなげたものです。
- Attention(注意): 広告や店頭などで商品を知り、注意を引かれる段階。
- Interest(関心): 商品についてもっと知りたいと思い、関心を持つ段階。
- Desire(欲求): 商品を欲しいと思うようになる段階。
- Memory(記憶): 商品の情報を記憶し、必要に応じて思い出せるようにする段階。
- Action(行動): 実際に商品を購入する段階。
次にAIDMAの法則の各段階について説明します。
それぞれの段階を具体的に見ていきましょう。
Attention(注意)
消費者は、テレビCM、インターネット広告、店頭のディスプレイなど、さまざまな情報に触れる中で、ある商品の存在に気づきます。
この段階では、いかに消費者の注意を引くかが重要となります。キャッチーなコピー、印象的なビジュアル、斬新なデザインなどが効果的です。
例:テレビCMで流れる魅力的な映像や音楽、SNSで話題になっている投稿など。
Interest(関心)
注意を引かれた消費者は、その商品についてもっと知りたいと思うようになります。
商品の機能、特徴、メリットなどを調べ、自分のニーズに合致するかどうかを検討します。
例:商品のウェブサイトを閲覧する、レビュー記事を読む、口コミをチェックするなど。
Desire(欲求)
商品の情報を収集するうちに、消費者はその商品を欲しいと思うようになります。
商品の持つ価値や魅力に惹かれ、購入することで得られる満足を想像します。
例:「この商品があれば生活がもっと便利になる」「この商品を使えば周りから注目される」といった感情。
Memory(記憶)
すぐに購入に至らない場合でも、消費者は商品の情報を記憶にとどめます。
必要な時にその情報を思い出せるように、頭の中や記録媒体(お気に入りリストなど)に保存します。
例:商品の名前や特徴を覚えている、ウェブサイトをブックマークする、SNSの投稿を保存するなど。
Action(行動)
最終的に、消費者は商品の購入を決断し、行動に移します。
店舗で購入する、オンラインストアで注文する、サービスを申し込むなど、具体的な行動を起こします。
例:店舗に足を運んで商品を購入する、ECサイトでカートに入れて決済する。
AIDMAの法則の活用
AIDMAの法則は、マーケティング戦略を立案する上で非常に役立ちます。各段階に合わせて適切な施策を講じることで、消費者を購買へと導くことができます。
Attention(注意)段階: 広告、イベント、キャンペーンなどで認知度を高める。
Interest(関心)段階: ウェブサイト、カタログ、説明会などで詳しい情報を提供する。
Desire(欲求)段階: デモンストレーション、試用体験、口コミなどで購買意欲を刺激する。
Memory(記憶)段階: リターゲティング広告、メールマガジンなどで情報を想起させる。
Action(行動)段階: 購入しやすい環境を整える(オンラインストアの使いやすさ、店舗へのアクセスなど)。
AIDMAの法則の課題と変化
インターネットやスマートフォンの普及により、消費者の行動は多様化しており、AIDMAの法則だけでは説明しきれない部分も出てきました。そこで、以下のような新しいモデルも提唱されています。
AISAS(アイサス): Attention(注意)、Interest(関心)、Search(検索)、Action(行動)、Share(共有)
AISCEAS(アイシーズ): Attention(注意)、Interest(関心)、Search(検索)、Comparison(比較)、Examination(検討)、Action(行動)、Share(共有)
これらのモデルは、インターネット上での情報収集や共有といった消費行動をより反映したものとなっています。
しかし、AIDMAの法則は、消費者の心理プロセスを理解する上での基本的な枠組みとして、今でも重要な意味を持っています。変化する時代に合わせて、これらのモデルを適切に使い分けていきましょう。
どこから手を付けるべきか
AIDMAの法則をせっかく身に着けたので早速行って頂きたいことがあります。
それはウェブ広告の確認です。
競合店のホームページを見て、自分のお店のホームページのほうが魅力的か、広告を出稿している場合も競合店の広告より注目される広告かどうか。
この2点を徹底的に見直すことで来店客数を増やしていきましょう。
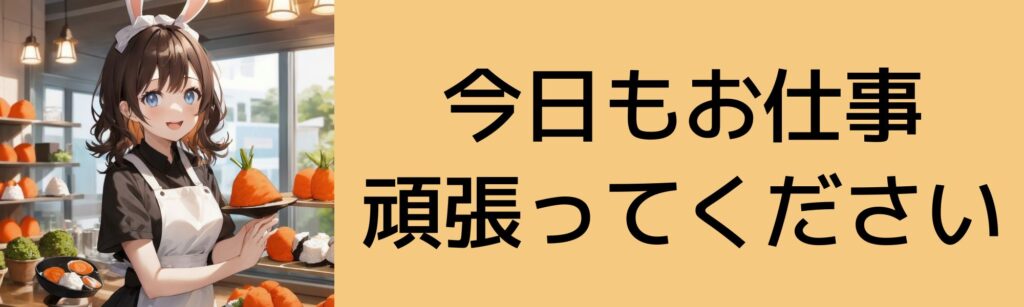

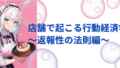
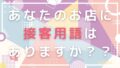
コメント